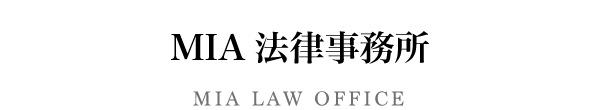No products in the cart.
遠隔医療について
問題提起
遠隔医療の良いところ
- 病院・医院に行かなくとも、診療が受けられる(患者側)
- 足腰が悪い場合でも診療してもらえる(患者側)
- 多くの顧客が獲得できる(医療機関側)
遠隔医療の悪いところ
- 面前ではないので、見落としの可能性がある
☆訴訟リスクが拡大する…今回のメインテーマ
なぜ訴訟リスクが拡大するか
医療機関から見ていきましょう。
医療機関は、一部を除いて、基本的に経営状態が悪いところはそこまでありません。
とすると、欲をかかなければ通常、直接診ない遠隔医療に手を出しません。
実際、医療の基本であり、視診・触診ができないので、通常の感覚の医師であれば、わざわざ遠隔医療を行う必要がないのです。
医療機関側の視点
また、通常の医師であれば、見落としや誤診が怖いのです。
面前であってもそれが怖いのですから、画像の制度がどんなに高まったとしても遠隔地は怖いと考える医師が通常です。
では、遠隔医療を行うのはどのような場合か。
これは、先ほどのように、遠隔地で医療機関に通うのが困難な方のために、という場合だけと考えるべきでしょう。
損をしてでも患者さんのために、という医療機関のみ遠隔医療を行うべきというのが現状でしょう。
患者さん側の視点
遠隔医療と聞くと、医療機関に行かなくとも医療が受けられると考えるところまではその通りですが、病院に行ったのと同様の医療を受けられるという期待を持っている。
実際には、診察精度は落ちるが、その期待は変わらない。
しかし、もし何かあった場合には、面前で診察をしていたのと同様の責任を医療機関に追及してくる。
遠隔医療提供者の問題
医療訴訟というと、通常、医療機関と患者さんとが、良くない結果について医療機関の過失を問うものと考えられます。
しかし、現状では、遠隔医療によってその画像精度等の問題が生じた場合には、その医療機関と患者さんとを結びつけるメーカーの責任もクローズアップされることになります。
もちろん、約款等で医療機関に対して、悩ましい場合には、直接面前で診察するように、などと促すことでしょう。
しかし、患者側としては、メーカーと医師とを共同被告として訴えることが予測されます→民法719条共同不法行為
その他の問題
実際に裁判になって医療機関側が負ける一番のパターンが、その病気に気が付きながら、検査や治療、手術が遅れて、最悪の結果になるという場合です。
遠隔医療の場合には、患者さんが訴えた場所以外を網羅的に見ることができません。
しかし、遠隔医療だから言われた部分しか見ていない、とは言えないのです。
医療機関であれば、何か他に予兆があれば、その部分についても気が付かない分でも、スクリーニング的に診察することが求められます。
そうすると、そもそも遠隔医療については危険しかありません。
では、遠隔医療は不要なのか
答えはNoでしょう。
正しい使い方をすれば、非常に有意義なものと考えられます。
それはどのようにしたらよいか…
【医療安全】についてしっかりと対策をするということです。
具体的には、裁判になった際を見据えて、その危険性について絶えずチェックする仕組みを作り、運用をしていくということです。
遠隔医療における医療安全
これは、医療関係者でも、医療機器メーカーでもできません。
弁護士でも通常の弁護士ではできません。
医療について熟知している弁護士の関与が絶対不可欠なのです。
その具体的内容について次のスライドから説明します。
司法との付き合い方の過ち
病院から開業医に至るまで、有事の際になるまで顧問弁護士が医療に関わらない
そもそも、顧問弁護士が医療に関わるという文化が受け皿としての病院や開業医にもない
顧問弁護士自体にも、医療に関わるだけの知識・能力もない
遠隔医療サービス提供者には、医療について弁護士程度の知識・能力しかない。
※医療と司法の橋渡しが重要
そのために大事なこと〜結論
医療機関や医師・医療関係者にとっては、「司法」に対して理解の姿勢を示すこと
司法にとっては、医療現場に足を運び、医療現場の感覚を理解すること
遠隔医療提供業者は、いずれにも理解することが必要
医療は裁判になじまない
弁護士のほとんどは患者さんと同程度の医療知識しかない
裁判官も判決を書きたくないというのが実情→医療集中部でも
しかし、裁判官は自分の論理で動く
おかしな判決は医療現場に書類作成という形で負担を与えていく
→医療機関の業務負担の増加
※今すべきは、医師その他の医療スタッフが証拠作りという認識をも持ってカルテや看護
記録などの書類を作成すること
※遠隔医療についても、医療スタッフが法的問題点について熟知していることが必要。
※それはそのまま医療安全に通ずる
これまでの医療機関と顧問弁護士との関係
医師会の顧問弁護士がいるからと顧問弁護士を持たない
顧問弁護士がいるが、ゴルフやロータリーの付き合い、若しくは高校時代の同級生、などという理由で選んでいる
弁護士として経歴が長い、役職経験者だからという理由で顧問契約を結んでいる
遠隔医療提供業者も、医療と司法と橋渡しの重要性についてよく分かっていない
※医療の専門ではない弁護士がとりあえずいる、というのが実情
医療訴訟の仕組み〜過失と因果関係
「過失」→「〜すべきだったにも関わらず〜しなかった」
・「因果関係」→「あれなければこれなし」
※ポイントは、〜すべきであった、あれなければ、というのは、日常の医療体制のことをいうという点です。その日常の医療体制に遠隔医療提供サービスも含まれます。
医療訴訟の仕組み〜交通事故との比較
交通事故・・・どんなに気をつけて運転していたとしても、事故が生じた場合に、運転手は原則として責任を負う。
医療事故・・・気をつけてさえいれば、不幸にして事故が生じたとしても、医療機関や遠隔医療提供業者には責任はない、
※すなわち、【気をつける】という点が大事
※有事の際にしか動かない弁護士は意味がない
医療訴訟の対策(=医療安全)
医療訴訟で扱われるのは、
- カルテの記載
- 看護記録の記載
- 同意書の取り方、記載方法
- 医療体制・倫理委員会の開催・議事録
- 日ごろの安全体制に対する意識の程度
※これらは証拠として使われる→常に証拠として作成する意識が必要
医療訴訟の対策2
医療安全体制の構築のために弁護士がすべきこと
- カルテの記載を日常的に抽出した上でチェック
- 看護記録の記載を日常的に抽出した上でチェック
- 同意書の取り方、記載方法をチェック
※これらについてスタッフ講習等が必要
医療体制・倫理委員会に弁護士が加わり、手続きの適正をはかり、また、いざという時に意味のある法的書面を作成する
日ごろの安全体制に対する意識を高めるために、定期的にスタッフ講習を開催
弁護士側の問題点
前述のように、医療については、素人同様の知識しかなく、何か相談しようと思っても、患者さん並みの知識しかないので、相談にならない。
弁護士の側としても、古き良き時代に勉強せずとも顧問料をもらい続けてきた結果、わざわざいまさら医療について勉強しようとするモチベーションがわかない。
結果として、医療機関に適切な指導ができず、マスコミによる医療バッシングが生じることになる。
※少なくとも医療現場に定期的に足を運ばない弁護士は不要
※口頭での医療現場からの質問に一定の回答ができない弁護士も不要
弁護士側の問題点2
医療訴訟の何割かは医療をわからない医療機関側の弁護士によって裁判になっているという実情
説明会の際に、患者さん側に不信を持たせてしまう
患者さんと信頼関係があるのは医師であり、弁護士ではない。そのことが根本的にわかっていないのが主因
医療機関側の問題点
問題のある顧問弁護士と気付きながら放置している
これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だと思い込んでいる
明日は我が身という意識がない
※リスクマネージメントという意識が大事
Ex.前橋で起きた高畑淳子の息子の強姦致傷の事件
・・・経済損失は計り知れない(数億円とも??)
※例えば誰か1人男性マネージャーを同室で宿泊させているだけで違った
→当然それだけの財力はあるはず…損失を考慮すると大した金額ではない
医療機関側の問題点2
有事の際でも、結局示談屋として弁護士が動いているのみ〜その事件は解決しても、問題は解決しない結局、リピーターとなる→その医療機関の体質が改善できないから
悪循環に陥る〜負のスパイラル
→評判が落ちる
→スタッフ離れの原因となる
→人員不足によりさらに事故が起きやすくなる
医療安全体制を構築しなければならない理由
日本では、刑事責任を追及される可能性がある
⇔諸外国ではまず医師が刑事責任を追及されることはない
日本では、担当医が最大の責任者という傾向
⇔諸外国では立場が上の医師ほど責任は重くなる
※例えば大学病院なら、病院長→教授→医長→担当医の順に責任が重くなる可能性がある
※例えば、総合病院なら、病院長→部長→医長→担当医の順に責任が重くなる可能性がある。
刑事責任との関係について
罰金刑以上の刑→医道審議会で審議の対象となる
業務上過失致死傷→過失の有無が問題
刑事事件の過失>民事事件の過失…刑事事件の過失の方が重い
※医療安全体制構築をしていれば、刑事事件はほぼ防ぐことができる
組織の責任について
組織で生じたことの責任は、組織の長がとる
末端の医師による事故も、その医師が悪いのではなく、そのような医師を管理しなかった長が悪いという考え方
今、パラダイムシフトしてきている→これまでのように医師が自分の医療行為についてのみ責任を負うという構図ではなくなる可能性
組織の責任について2
長は無限責任を負わされるのか→NO
→それでは誰も長をやらなくなってしまう
長は、結果責任ではなく、コンプライアンス体制構築責任を負います。
※つまり、医療安全体制をしっかり構築し、それを継続していれば、結果として不幸な事故が生じたとしても、長の責任はない
※そのような管理体制をとらなければ重い責任を負わされるということ
組織の責任について3
会社経営者は既にこのようなルールで責任を負っている
経営判断の原則という考え方
なぜ医療にはこのような考え方の導入が遅れているのか
病院単位では、病院の責任ということで病院長が頭を下げるということが通常となってきている→組織責任の兆し
弁論主義とは
これは民事裁判のルール
当事者主義から派生する考え方→裁判官は当事者の言い分のみから原則判断する
双方弁護士がきちんと主張していなければ判決もおかしなものとなる
おかしな判決は先例とならない
医療現場について詳しい弁護士が皆無なため、先例となる判決はほとんどなかった
医師は自分の身を自分で守る時代
自分の免許は自分で守る→刑事事件は組織責任ではない
組織で立場が上になれば、責任も重くなる
医療行為以外についても刑事事件に巻き込まれる可能性がある(医師法違反・診療報酬詐欺など)→けっこう多い
医師以外の資格職は弱肉強食となってきている〜医師もいつまでも安泰ではない
※リスクマネージメントが求められている→そのために弁護士を活用すべき
医療安全に取り組むとこんないいことが・・・
自分のしている医療行為の法律的な裏付けができて、自信を持って医療を行うことができる。
スタッフも医療行為に自信がもて、萎縮することなく医療が行える。結果として、患者さんに対して向かい合う時間が増え、患者さんの満足度も高まる。
患者さんの満足度が高まれば、経営が安定化され、頼りになる病院としてブランド化していく。
トラブルが生じる確率が圧倒的に減り、また、万が一トラブルになったとしても、大事になる確率は減る。訴訟にまで行く確率はもっと減る。
社会から信用を得ることができれば、地位も安定し、名誉ある立場に立つことができる。
弁護士の活用法
①定期的に医療現場に弁護士に来て現場指導をしてもらうようにしましょう。
※病院・医院の規模にもよりますが、手術開業医で3か月に1度くらい、規模が大きければこれより多く、規模が小さければこれより少なくて良いと思います。
※来てくれない場合は、顧問弁護士契約を打ち切り、来てくれる弁護士を探しましょう。
②弁護士が定期的に来たとして、少なくともポリクリ学生程度の医療の知識がなければ、それは意味がありません。しっかりと見定めましょう。
※難しい医学知識までは裁判上不要ですが、基本的な解剖知識すらなければ話になりません。
※持ち帰ってから後で回答するという姿勢の弁護士ではなく、その場で一定の回答ができる弁護士を探しましょう。
※正確にご回答させていただきたいといい、後で書面・メールで、というのはNG
弁護士の活用法2
③カルテ・看護記録の記載の方法に問題のある記載がないかを無作為抽出で日常的にチェック
→定期的に法律事務所にFAXするなど
④現場のスタッフの悩み等を直接弁護士に相談できる体制を
→メール・電話・FAXなど
⑤定期的にスタッフ講習を開催し、裁判との関係で、やってはいけないカルテ・看護記録の記載や、意味のない同意書等についてしっかり教育してもらう
⑥倫理委員会や、医療安全委員会に参加してもらい、手続きの適正をはかるとともに、議事録を法的に意味のあるものとして残し、いざという時に備える。
さいごに
これまで、医療と司法とは乖離し、理解しようにも互いに理解することが困難な分野でした。その結果、司法に対する信頼は揺らぎ、医療現場は混乱するという事態を招いたことは言うまでもないことでしょう。
弁護士=訴えられたら頼むという構図に固まってしまったことから、種々の問題が生じてしまったことはこれまで説明した通りです。
これからは、裁判にならないようにするために弁護士を「事前」に活用すべき時代です。
これは安心・安全な医療の提供につながります。すなわち、医療訴訟予防=医療安全なのです。
2016年11月日本遠隔医療学会にて(鳥取)